問題に直面するとAIに頼る大学生 回答者の8割が「友達」と見なす

(写真著作権は視覚中国が所有のため転載禁止)
中国青年報・中青校媒がこのほど、SNSアプリ「Soul」と共同で、中国全土の大学生を対象に、AIツールの使用と、それに対する姿勢に関するアンケート調査を実施し、3129人から有効回答を得た。調査結果によると、回答者の99.2%が「AIを使っている」と答え、そのうちの11.7%がほぼ毎日何度も使う「ヘビーユーザー」だった。また、65.9%が「なにか問題があると、無意識のうちにまずAIに助けを求めている」と答えた。中国青年報が伝えた。
大学生約半数が「AIなしでは生活できない」
中国海洋大学でジャーナリズム・コミュニケーション関連の専門を専攻している孫一丹さんの日常生活において、AIは情報をふるい分けるサポーターであり、複数の情報源を集約して、抜粋した回答を得て、さらに、その情報源のリンクを残すことで、検索エンジンでむやみに検索するのを避けている。動画編集ソフトウェアのAI機能は、動画制作関連の難題を解決している。ワンクリックで、字幕をスマート認識し、自動で適切な時間軸に合わせて配置することができる。AI脚本機能もキーワードに基づいて、ストーリーの大筋を生成してくれるため、エネルギーの節約につながっている。過去1年にわたり、孫さんのAIに対する依存は大幅に高まったという。広告・企画案を立ち上げる前に、AIにブレインストーミングさせ、10個のクリエイティビティな方向性を生成してもらうというのが習慣となっている。日常生活において、AIは毎日、彼女の必要に合わせたテクノロジーやメディア関連の話題を送り、「人が情報を探す」から「情報が人を探す」への変化を実現している。
AIが発展するにつれて、情報検索のスタイルやツールは、世代交代とシフトがその流れとなっている。アンケートに回答した大学生が情報を得るための選択肢として、満点を5ポイントとした場合、AIツールは3.34ポイントを獲得しており、従来の検索エンジン(2.60ポイント)やソーシャルメディア(2.81ポイント)を抑えて第一の選択肢になっている。回答者の65.9%は、日常生活や仕事、学習において、問題に直面すると、無意識のうちに、まずAIに助けを求めていると答えた。
また香港中文大学で学ぶ景哲さんにとって、科学研究の模索の際、AIが有能なアシスタントとなっており、「AIの議論ロジックは非常に厳密で、頭をひねっても、思考の抜け穴が見つからない場合があるが、AIはそれを速やかに指摘できるほか、考慮できるたくさんの反例を提供することもできる」という。
調査では、回答者の47.1%が「AIなしでは生活できなくなっている」と感じており、そのうちの10.5%が「絶対になくては困る」と答えた。36.5%は、「どちらかというとないと困る」と答えた。資料・文献チェック、テキストの磨き上げ、翻訳、総括・報告といった文章作成が、回答した大学生に最も人気のAI応用シーンで、全体の43.0%以上を占めていた。調査では、大学1年と2年生を見ると、「資料チェック」、「画像生成」、「会話の練習」、「知識学習」、「翻訳」、「模擬面接」といったシーンにおけるAI応用が最も多かった。大学3年と4年生を見ると、「求職アドバイス」、「データ・統計」、「コード作成」、「オーディオ・動画編集」、「会議記録」といったシーンにおけるAIの使用が最も多かった。
雲南師範大学で中国言語文学を専攻している崔佳一さんにとっては、日常生活の中でAIの対話機能が、「アシスタント」となっている。彼女は、旅行専門アプリと組み合わせて、AIに旅行の嗜好、予算、目的地を伝えるのが習慣となっており、「例えば、『雲南省の歴史的景観があるニッチな場所で、1日当たりの予算は500元(1元は約20.8円)。辛い食べ物が好き』と伝えると、AIがすぐに、スケジューリングして、沙渓古鎮のようなニッチな観光スポットや、現地の野生のキノコ類を炒めたピリ辛料理が食べられるレストランなどを教えてくれ、自分で攻略ガイドをチェックするよりよっぽど速い」と話す。
調査では、生活常識チェック(48.3%)、旅行のスケジューリング(40.3%)、運動やアートの初心者向けガイド(37.0%)、画像・動画編集(36.3%)、人間関係に関する提案(35.0%)などが、回答した大学生の生活において、AIを応用することが多いシーンとなっていた。
大学生8割がAIを「友達」と見なしたことがある
データによると、回答者の8割が、「AIをおしゃべり相手にしたことがある」と答え、AIをある意味で「友達」と見なして、交流した経験があるとの回答もあった。また、4分の1以上(26.0%)が「落ち込んでいる時に、自分からAIに慰めや情緒的価値を求める」と答えた。その割合は、「ソーシャルメディアを通して、ネットユーザーの意見を求める」の支持率(26.2%)とほぼ同じで、感情的な寄り添いという分野に、AIが深く浸透していることを示している。
華中師範大学の人工知能(AI)教育学部の呉砥教授は、「AI技術は当初、大学生に学習ツールと見なされていたが、その能力が徐々に高まり、幅広く受け入れられるようになるにつれて、使用頻度が高まり続け、徐々に仲の良い『学習パートナー』になった。さらに、仕事や生活のさまざまな面にも浸透するようになり、ひいては技術を通してエンパワーしてくれる『心の知能指数(EQ)が高い』パートナーにさえなっている。AIはいつでも使え、疲れることもなく、自然言語処理能力も非常に高いため、誰かと繋がっていたいものの、ばつの悪い思いをするのも怖いという大学生のナイーブな時期の心理的ニーズを満たしてくれる。一部の学生は、他の人と交流する点で不安を感じていたり、スキルが不足していたりしており、AIはフォロー役として、安全でリスクの無いバーチャルソーシャルプラットフォームを提供し、能力を高め、不安を和らげることができるようサポートしてくれる」と分析する。
一方で、回答した大学生が、落ち込んでいる時に、悩みを打ち明ける対象として一番多かったのは「友達」(72.6%)であることは注目に値する。それは、実際の人との繋がりが、感情を支えてもらう上でかけがえのない役割を果たしていることを示しており、実感できる感情的繋がりや安心感が依然として、本質的ニーズとなっていることを反映している。(編集KN)
「人民網日本語版」2025年9月23日

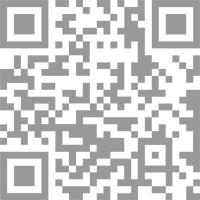 QRコードを読み取る
QRコードを読み取る